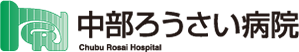中央リハビリテーション部
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- 中央リハビリテーション部
中央リハビリテーション部紹介
中央リハビリテーション部の特徴は脊髄損傷(脊髄障害)のリハビリです。脊髄の障害を神経学的評価に基づき障害のレベルに合わせてリハビリを進めます。
1000㎡ の開放感と抜群の採光量を誇る訓練室や屋外歩行訓練場での基本動作、応用歩行訓練など日常生活に必要なリハビリを行い患者さんの退院に向けての支援に取り組んでいます。

令和6年4月スタッフ数
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 3 |
|
理学療法士 (うち治療就労両立支援センター) |
23 (1) |
|
作業療法士 |
8 |
| 言語聴覚士 | 3 |
主な疾患
| 疾患名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 外傷性脊髄損傷 | 36 | 36 |
| 運動器疾患・外傷 | 784 | 844 |
| 脳血管疾患 | 303 | 379 |
| 呼吸器疾患 | 366 | 476 |
| 循環器疾患 | 209 | 233 |
| 外科疾患 | 125 | 123 |
| 神経筋疾患 | 56 | 51 |
| がん | 187 | 241 |
| 切断 | 16 | 10 |
| その他 | 846 | 951 |
【理学療法、作業療法】
理学療法では各診療科から依頼された疾患別(運動器・神経系・呼吸循環など)リハビリテーションを展開しています。近年では、呼吸器・循環器疾患の理学療法が増加傾向にあります。それぞれの疾患ごとに研鑽を積んだ理学療法士が専門的にリハビリを提供しています。また脊椎損傷による機能(運動や感覚)障害に対しても病態を理解し、麻痺の程度に応じたアプローチを段階的に実践できる経験豊富なスタッフが多数在籍しています。生活に必要な動作を効果的に再建するため車いすを用いた動作練習から歩行再建まで幅広い機能レベルに対応したリハビリを提供しています。その他、福祉用具の相談や情報提供、個人の体形に合わせた車いす(電動を含む)の採寸や処方を行い退院に向けて支援を行います。


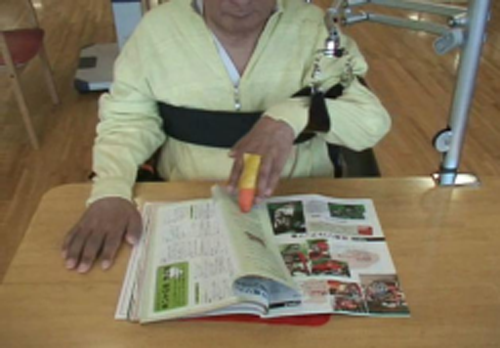
作業療法では、病床や訓練室で適宜段階に応じて介入しています。ベッド机上動作として食事や歯磨き、ひげ剃り等の整容動作、書字訓練、趣向的な読書やパソコン、携帯電話操作、またベッド上動作の寝返り・起き上がり、移乗、排泄・入浴動作などの日常生活訓練も行います。身体機能に合わせた自助具の製作や紹介、住宅改修・介護機器のアドバイスなど在宅復帰に向けたサポートも行っています。
1年に2回程度の割合で、車いす生活者のためのピアサポートを目的とした『社会生活講座』を、入院されている脊髄損傷の患者さん向けに中央リハビリ部主催で開催しています。「生活のこと」「身体のこと」「福祉サービス」「スポーツ」などのテーマに沿って、実際生活の中で経験・活動されておられる先輩方々から、役に立つ情報を見聞するというものです。


もう一つの特徴である切断肢に対するリハビリとして、リハ医・義肢装具士と連携をとり、早期に成熟断端形成を目指し、義肢による社会復帰訓練を行っています。
上肢切断者の作業療法では、断端成熟に合わせて仮義手を製作し、基礎訓練、両手動作訓練、日常生活応用訓練などを行います。
訓練用義手に関しては、ケーブルを介して動かす能動義手や筋の刺激にて動かす筋電義手などを義肢装具士と協力して行っていきます。 またその後、義手を使用した復職支援をサポートしていきます。理学療法による下肢切断者では、早期歩行獲得を目指し、断端管理・義足装着訓練・装着後の起立・歩行訓練を行っています。

【言語療法】
脳卒中などの脳の損傷により失語症や構音障害が生じる場合があります。
失語症とは、言葉を「聞く」「話す」「読む」「書く」などがスムーズに行えなくなる障害です。患者さんの症状を評価し、訓練を行ない患者さんのコミュニケーション手段の確保と、
円滑に会話ができるように支援しています。
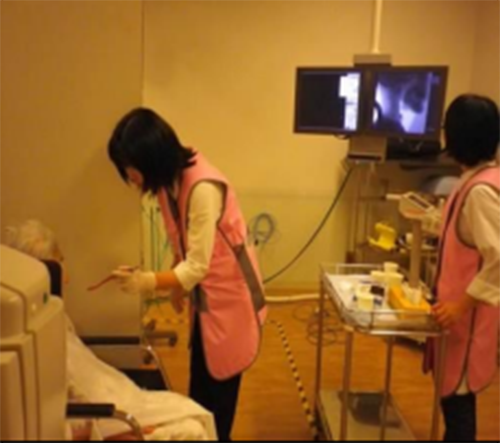

(摂食嚥下訓練)
飲み込みに問題がある人に対して、先ずは嚥下内視鏡検査(VE) や嚥下造影検査(VF)を行い、適切に評価をします。その結果をもとに口やのどの訓練をしたり、その人に適した食事の形態を決めています。
(チームアプローチ)
平成 24 年 2 月嚥下内視鏡検査(VE)導入とともにリハビリ医・嚥下障害看護認定看護師・栄養科・言語聴覚士で嚥下チームを結成し早期経口摂取を目指しています。
実績
| 検査 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| VE(嚥下内視鏡検査) | 10 | 19 |
|
VF(嚥下造影検査) |
465 |
518 |